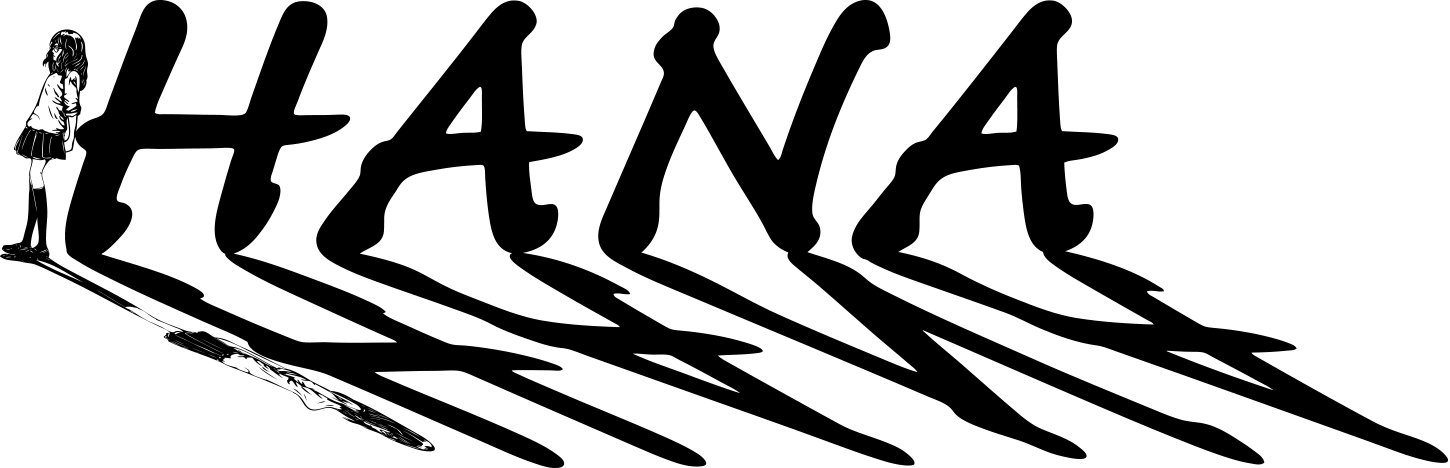ORIGINAL STORY

あらすじ
女子高生のハナは、顔もまずまず、そこそこモテて、成績も中の上。だけど、とっても胸が小さい。そんな彼女の誕生日に友人たちがプレゼントしたのは「おっぱいを大きくする薬」。翌朝目覚めた彼女の胸は……
原作『HANA』 結城紫雄 著
TV画面に「予約曲/歌手名/ブリーフ・アンド・トランクス」と表示されたのを確認して、空のグラスを手に立ち上がる。私はいつも絶妙のタイミングでコーラを飲み干す。まさに職人技。匠のストロー捌き。
「ドリンクバー行ってくるけど」
「ハナ、私メロンソーダ飲みたい」
オッケー、とキョウコに返事をしながらドアを足で押し開ける。涼しい風がカーデガン越しに心地よい。雑居ビル内の澱んだ空気が新鮮に感じるほど、私の呼吸器はこの三時間、体臭と香水とフリスクと各種デオドランド・スプレーとマルボロ・メンソール・ライトとその他諸々出所不明の臭いで侵され続けそろそろ限界だ。盛りがついた女子高生四人入りのカラオケボックスは、流石に暑くて苦しくて臭くて酸っぱい。ひょっとして誰か発酵しかけているのかしら(だとしたら間違いなくリツだ)、とぼんやり考えていたら、シュールストレミング、ブロッケンジュニア、くさや、そんな単語が次々と頭に浮かんでは消えた。
部屋に戻ると、案の定あの曲が大音量で流れていた。丁度後半のサビである。このメンバーでカラオケに行くと、ラストはこの曲でシメるという暗黙のルールがいつの間にか出来ているのが迷惑千万だが、もちろんそんなことはおくびにも出さない。今日も歌ってやろうじゃんか、ドリンクついでにフロントで借りたタンバリンを握りしめる。
ヒカリが「もう、ハナ遅いよ曲終わっちゃうよー」と愚痴っている隣で、「ハナがタンバリン持ってきてるー、超やべー」と笑い転げているキョウコの付けまつ毛がどんどんズレていって今はあんたの顔の方が超やべーよ、と思ったけど教えてやらないことに決めて、深呼吸ひとつ。さあ、ブリーフ・アンド・トランクスで『ペチャパイ』どうぞ!
リツ、キョウコ、ヒカリが三人で「ぺーちゃぱい!」と唱和した後に、私にマイクを渡してくるので、大声で歌い返す。咆哮する。
「ぺーちゃぱい!」
「仰向け苦しくない!」
「ぺーちゃぱい!」
「肩が凝らない!」
一同「ぺーちゃぱい!」
私「お風呂あふれない! カバン食い込まない! ノーブラでもバレなーい!」
一同「(せーの)ハナの胸はー」
私「トリプルA!」
ねえ。そんなの原曲にねえよ。
む、虚しい。ハナのは虚しい乳と書いて「きょにゅう」だね、なんてアンタはウマいこと言うよ、リツ。
リツ曰く、私の胸といえば、この学校で知らない者はない。歩く関東平野、JKプレートテクトニクス、ぺったんこカン・カン、異名をあげればキリがない。目線を下にうつせば、腹の膨らみから爪先に至るまで全て視界に入る。ヒカリは次元が違うから諦めろという。彼女が言う次元とはレベルという意味ではなく、三次元か二次元かの違いなのだそうだ。
かつて私は、大人になれば勝手に大きくなるもの、それが乳房というものであると思っていた。幼児特有の実に安易な発想である。身長が百六十少しで止まり、お赤飯をいただき、厄介な無駄毛が生えてきたところで、私の第二次性徴はあっけなく終焉を迎えた。これが有名進学高校だったら、「未履修科目があるのに卒業させるとは何事か」と大問題になるのは間違いない。
物心ついたときから形態が変わらない我が胸のせいで、「ブラジャー」といえばナイキとかエレッセとか、とにかくスポーツ・ブランドのロゴが入っているものだと思っていた。それがいわゆる「スポーツブラ」と呼ばれるブラ界のマイノリティーにしてカースト底辺であることを知ったのは高校入学してからで、入学直後の体育の授業前、三本アディダスラインのブラを見たリツたちが呼吸困難になるほど爆笑した、という小さな事件がおこり、私は普通の下着へとシフトするタイミングを失ってしまう。幸か不幸か、高校生活における私の「貧乳いじられキャラ」もここで完全に定着しまったのである。ゆえにハナの貧乳といえば、この女子高で知らない者はない。
もちろん、胸の大きさは気になる。しかし私が一番怖れているのは、胸自体のことよりも、自分が胸にコンプレックスを抱いているという事実を他人に悟られることだ。話の中で「胸」「バスト」「カップ」「乳」「おっぱい」「π」という単語がでてくる度に私の鼓動は高まる。口の端がひきつってやしないか、伏せ目がちになってやしないか。そして適度に相槌を打ち、なおかつ話の中心からは距離を置き(特にどこのメーカーのブラがいいか、とかの話題は非常に困る)、さりげなく話題の方向転換を計らねばならない。我ながら狡猾かつ滑稽なまでの必死さである。
むしろこういった話題よりも、単刀直入に私の貧乳を笑い飛ばしてくれたほうが幾分マシと言えよう。しかし中には、私の胸を真剣に心配しやがる輩もいる。「小さな親切、大きなお世話」がこいつらのモットーに違いない。
ある日の昼休み、学食のサラダを食べながらヒカリ(そういう輩A)がニヤニヤしながら口を開いた。
「あたし『アンアン』で読んだんだけどさー、キャベツって胸おっきくする効果があるらしいよ?」
「えー知らない。聞いたことないってゆーか興味ない」
まさかもう実験済み、そして効果の有無も実証済みとは乳が裂けても言えまい。
「健康にもよさそーじゃん。試してみなよー」
「いいよ私別に。気にしてないし、巨乳になったら可愛い服とか着られないじゃん」ね、とニコリ。不自然じゃない、上出来。 「あたしも聞いたことあるそれ」キョウコ(輩B)が焼きそばパンを頬ばりながら喋る。食べながら話すな。というか、胸について話すな。
「たしかねー、『デロン』て成分が胸に効くんだって。いかにも大きくなりそうな名前じゃね? デロン、デローンって」
「ちょ、なにそれウケる。頑張れー、あたしのデロンー」
でろーん、でろーん、とヒカリとキョウコが互いの胸に手をあててはしゃいでいるのを見て、私は深くため息をついた。彼女たちのような半端な知識のひけらかしが一番頭にくる。
「それ言うなら『ボロン』でしょ! 何よ、デロンデロンて、馬鹿みたい」
一瞬黙った後、二人は同時に口を開いた。
「ハナ、めっちゃ詳しいじゃん」
私はひどく赤面した。
別に胸が小さくても構わないのである。顔はまあまあイケてるし、そこそこモテるし、勉強だって学校では中の上の成績だ。胸の小ささが私を悩ませているわけでは断じてない。私は実にこの胸によって傷つけられる自尊心のために苦しんでいるのである。しかし私の、いや私に限らず年頃の乙女一般の自尊心は「顔や彼氏がどーのこーの」というような結果的な事実に左右されるためには、あんまりにもデリケイトかつプラトニックはたまたセンシティヴに出来ていたのである。
もちろん、胸を大きくする方法があると聞けば、積極的に実践した。豆乳、リンゴ、そしてキャベツ。サプリメントや雑誌の巻末に載っている怪しげな薬に器具、マッサージ、スピリチュアル療法、おまじない、自己暗示、祈祷、エトセトラ、エトセトラ。しかし満足いくほどの効果が出たことは一度もない。
ならばと、巨乳アイドルがもてはやされる日本を捨てて、貧乳がもてはやされる社会をこの地球上に求めたことがある。そんな乳楽園(ニュートピア)は意外にも簡単に見つかった。EUの雄、フランス共和国である。なんでもこの国の民衆には、「巨乳は頭が悪そう」という考えから貧乳が非常に好まれるらしい。偉大な仏人哲学者の「胸は小さいほうが良いように思える。なぜなら、触れたとき心に近いからだ」という格言は私を歓喜させた(急いでスマホにメモった)。しかしよくよく調べてみると、フランスにおける貧乳ブームは一七〇〇年代のことらしい。私は唸った。せめて三十年周期ぐらいでブームが来てくれないと困る。
自分の胸を気にしていると、他人の胸も当然気になるもので、学校にいるとついつい友人の胸に目がいく。水泳の授業中では自分より小さい胸を持つものはいないかと目を皿のようにしているのだが、いまだ我が校には見当たらない。それどころか、同じような胸をした生徒がすれ違いざまに「あんたには勝った」という目をするのが頭にきて仕方がない。しかも本当に負けているからやるせないのである。
加えてDカップを自称するリツが「あたし最近しぼんじゃってー」などと抜かしていたのを聞いたときには思わず耳を疑った。
「あんたねー、そんな胸あるのに贅沢だよ」
「なんかダイエットしたら胸だけ肉落ちちゃってさー」
「Dカップです、なんて私にとっちゃ『私の戦闘力は五十三万です』、て言われた気分だわ」
「じゃあハナは戦闘力二か……ゴミめ!」
その日の放課後、私は「スポーツを通じていかにして青少年の剛健なる魂を育成し健全な社会を形成するか」という題で二千字の反省レポートを書くよう、体育教師に命じられた。カナヅチのリツをプールに突き落した件で。
「最後のプール楽しみにしてたのにー」
ヒカリがアイスを舐めながら私をニラむ。だからあんたらにお詫びのアイスを奢っているではないか。
「まさかハナとリツのせいで授業中断しちゃうなんてね」とキョウコ。こいつは溺れて失神したリツを写メっていた。彼氏とそれを見ながら大いに盛り上がるがよい。
「あたしなんてハナに突き落されて溺れ死にかけたんですけど」つくづくリツは大袈裟だと思う。口から泡吹いたぐらいで。 レポートを書き終え、保健室で息を吹き返したリツ、教室の隅で「コーラを使用した避妊の成功率」について熱心に議論していたヒカリ(ペプシ派)とキョウコ(ダイエットコーラ派)たちと下校する。九月も終わりに近づき、プールの授業が不本意な最終回を迎え、風も大分冷たくなった。 「そういえばハナ、もうすぐ誕生日じゃん」
夏生まれのリツ、ヒカリの誕生日はみんなでお祝いをしてプレゼントを贈った。キョウコは彼氏持ちなので他人の誕生日会は参加するが、彼女自身の誕生日に私たちは何も贈らない、というのが一応のルールである。
「何ほしい? 彼氏? 寒い時期の独り身はつらいですからねえ」とおどけるキョウコをリツが睨む。
そうなのだ。私は十月に生まれた。紅葉が綺麗だったので、母は初め「紅綿子」と名づけようとした、という微笑ましい、もといトチ狂ったエピソードは高一だった私を凍りつかせた。何を隠そう、読みは「もみこ」である。トリプルAカップで名前がもみこちゃん、どう好意的に解釈してもギャグとしか思えない。しかし名は体を表す、という諺も確かに存在するな、と一時期考えたのだが、思えば改名して成功した有名人など一向に思い当たらないので、結局私の名は「ハナ」のままである。
「貧乳を馬鹿にされて友達を失神させたって、もうC組でも噂してたよ」ああ、また私の貧乳が知れ渡るのか。頭が痛い。心はもっと痛い。
「ハナ、おっぱい大きくする薬あげようか?」
私はヒカリの頭を思いっきりはたいた。
「はい、おっぱいを大きくする薬だよー」
私の十七歳の誕生日。いつものカラオケボックスでリツが差し出したのは、一粒の白く小さな錠剤であった。表面に「D」と印刷してある。
「なにこれ。ビレバンとかで『恋に効くクスリ』とかの横に売ってるやつ?」
私はあきれた。「○○に効くクスリ」は以前流行した、雑貨屋などに置いてあるただの飴である。要は単なるおまじないだ。
「違うよ、マジに効くんだってば」
隣のキョウコ、ヒカリの目も珍しく真剣だ。茶化しているようには思えないが、飴じゃないとしたら、麻薬とか、合法ドラッグとか、脱法ハーブの類だろうか。何より、あれだけ豊胸のためのサプリを試した私が初めて目にする薬なのだ。明らかに危険な香りがする。やはりただのジョーク・アイテムの仲間なのだろう。
「あーあ。リツの誕生日にはみんなでサマンサのピアスあげたのになー。私には飴玉かあ」
だから違うんだってば、と言うリツの話によるとこうである。彼女の大学生になる姉が、夏休みに治験のアルバイトにいった。治験とは未だ認可されていない薬を被験者に飲ませ、その後の検査で効果を見るというものだ。十日前後の検査で、報酬(正確には謝礼という。治験はあくまでボランティアであり給料は発生しない)は数十万という場合もある。しかし副作用が出たとしても自己責任だというから、要は公認の人体実験だ。
「一週間も泊まらされたあげく、煙草も酒も禁止なんだってさ」
「うわーダルい」ダルいもなにも、私たちは未成年である。
リツの姉が試すことになったのは、新しい導眠薬の実験だったらしい。一回三錠を一日二回。確かに眠たくはなったらしいが、そんなことよりも副作用が問題だった。Bカップだった胸が、二日目午前の時点でDカップになってしまったのだ。それに驚き、体への悪影響を怖れた医師が以後の服用を禁じた。薬の配布は一日一回なので、彼女は午後の分の薬も持っていたが、医師に服用を止められたためちゃっかり持ち帰ったらしい。
その薬こそが、今リツが手にしている錠剤なのだ。彼女の話を聞いたリツたち三人が、キルフェボンのケーキ一ホールと引き換えに手に入れたのだという。
「なるほど」
私は頷いた。治験段階でしか知られていない未承認薬。私が知らないのも無理はない。気になるのが副作用だ。説明によると豊胸効果そのものが副作用みたいなものだが。
「副作用は、今のところナシ」
私の懸念を見透かしたかのように、リツが言った。
「むこうもビックリしてさー、バイト期間終了してからもずっと検査の連続だったよ。でもお姉ちゃん胸が大きくなっただけで何も病気とかしてないしさー、おまけに彼氏できるし、めちゃくちゃモテだしたみたいだし」
なんだかカルト宗教の勧誘みたいだ。
「じゃあ、この薬の『D』ってのはDカップのD?」
「いや、『DEKAPAI』のDじゃね?」
「リツはバカだな、『DOUMINZAI』のDだろ」
「うーん」
私は唸った。リツの話を聞く限り、試してみる価値が全く無いとは言えない。むしろ、怪しげな通販よりもよっぽど信用できる。製薬会社の治験で配られた薬だし、そんなに危険なものでもなさそうだ。
しかし問題はまた別のところにある。今まで「胸なんて気にしておりません」という毅然とした態度を貫き通した私だ。はあそうですか、と言って薬を飲むのは簡単だが、それでは癪というか、何よりも自尊心が許さない。
「やっぱ、私やめとく」
「えーなんでよ」
「そんな危ない薬飲めないし、私はこのままで十分なの」
「うそだー」
リツの一言に私の心臓がドクン、と大きく音をたてた。
「ハナいっつもブリ&トラの『ペチャパイ』いれたらさー、トイレとかドリンクとか言ってどっか行っちゃうじゃん。ホントは気にしてんでしょ?」
コイツはアホそうな顔をして案外あなどれない。腋に汗がつたうのを感じる。
「気にしてないってば」
あくまで冗談ぽく流したつもりだが、動揺が伝わっているかもしれないと思うと不安がこみあげてきた。頬が火照っているのがわかる。ほぼ空のグラスを手にとり、底にたまった氷をじゃりじゃりと口に流し込む。
「そういえば」
口で氷を転がしながら、ふと疑問が浮かんだ。
「一回分が三錠って言ってなかったっけ? 残り二錠はどうしたの」
「ハナは飲まないんでしょ、関係ないじゃん」
なぜかリツはニヤニヤしている。ヒカリとキョウコも心なしか口元が緩んでいるように見えた。一体どうしたというのだ。
「……なによ。三人とも気持ち悪い」
「一つは、ここ」
ヒカリが手を開くと、同じ「D」の錠剤が見えた。
「なんじゃそりゃ、ヒカリも貰ったの?」
「違うの。三つともハナのだよ」
「で、もう一錠は?」
「もう一つは、そこに入れた」
キョウコが指差したのは、あろうことか私が手にしているグラスだった。ゴクン。
「ぎゃー!」私は悲鳴をあげた。
グラスは空っぽだ。飲んじゃったよ!
「それじゃ、今日帰ってあと二錠飲んでくださいねーお大事にー」
「何すんのよ!」思わず大きな声が出た。半分本気、半分ポーズで。
「ああでもしなきゃ、ハナ飲まないじゃん」
「もう飲んじゃったんだから、一錠も三錠変わんないって」
呆然とする私に、リツとヒカリが残りの錠剤を投げてよこす。 私はため息をついた。結局怪しい薬を飲むはめになってしまったのである。しかし実際は、三人で「私が仕方なく薬を飲むシチュエーション」を作ってくれたのだろう(多少の悪戯心はあったとしても、だ)。つくづくコイツらあなどれん、と思いつつ、ほんの少し彼女たちに感謝した。
「よーしじゃあ『ペチャパイ』歌って帰るか!」
人の誕生日なのにデリカシーの無いことこの上ない。結局、「ハナがDカップになったらもう歌えないじゃん」とせがむリツに負けて、最初から最後まで熱唱した。本当に最後になりますように、と念じながら。
「でろーん」「でろーん」 キョウコとヒカリがふざけて胸を触ってはキャアキャアはしゃいでいる。
「だからデロンじゃなくてボロンだってば」
苦笑いしながら、右の肩を揉む。最近、生まれて初めての肩こりに悩まされている。しかしその痛みすら今は愛おしい。
私の胸は今やリツ、キョウコ、ヒカリの誰よりも大きい。薬の効き目はてきめんだった。錠剤を飲んだ翌朝のことは今でも鮮明に思い出せる。あの夜はやけに寝苦しかった。六時間は寝たはずなのに、起きると体が前のめりになりそうでフラフラした。スリッパをはこうとすると、視界から足が消えていた……全てが己の胸のせいであり、しかもそれが一夜にして起こったことだという事実を認識するためには、少々時間が必要だったのである。
当然スポブラには収まりきれないので、慌ててリツに連絡し、その日は彼女のブラを貸してもらうことにした。しかし彼女のブラでもきつかったのだ、おそらくFカップはあるだろう。Fカップ! なんと柔らかそうな響きであることか。
私は一週間たった今でも、暇さえあればそっと胸をなでてみる。秋も深まり、冬服のブレザーを着ることが多いのだが、その厚手の生地の上からでもはっきりとした存在感を放っているのがわかる。大丈夫、今日も縮んでいない。薬を飲んで数日間は、噂を聞きつけた隣のクラスの生徒がわざわざ覗きにきたり、体育教師がやけに馴れ馴れしくなったり、生まれて初めてナンパされたり、Tシャツがほとんど入らなくなったので買い物に出かけたり、とかなり慌ただしい日が続いたが、最近はやっと落ち着いてきた。
周りの反応は(キョウコなど、初めは驚きのあまり声すら出せなかったほどだ)次第に薄くなってきたが、私の日常は段々と輝きだした。服や下着を選ぶのも楽しいし、早くも来年の夏が待ち遠しくてたまらない。何より自分に自信がついた。顔やスタイルは元から悪くないし、頭もいい。ここに胸が加わったのだ。鬼にカナボー、私にニューボーだ。リツたちから「ハナ最近顔も可愛くなった」と言われるが、やはり精神面の充実というのは外見に反映されるものなのだと実感する。
豊胸効果の影響かどうかは分からないが、隣の男子高校生に告白され付き合い始め、私の日常はこれまでにないほど充実していた。そしてその幸福は、永遠に変わらないように思われた。
ところが一か月も経たないうちに、私は意外な事実を発見した。
胸が大きくなってから数日間、私が廊下を歩くと友人はもちろん、話したことのない生徒や教師まで驚きの表情を見せた。言葉を交わしたことのある生徒であれは暫し驚いた後、どんなサプリを飲んだかを聞きたがり、「すごいじゃん」などと素直に称賛の言葉を口にした。しかしそれも一、二週間程度のことであった。「ハナが巨乳」という意外性が無くなるにつれて、彼女たちは明らかに私を嘲笑するようになったのである。最初は気のせいかとも思ったが、廊下を通る度に背後でくすくすと笑い声が聞こえる。いつも一緒にいたはずのヒカリやキョウコ、リツまで同じ素振りを見せるようになって、私ははたと困惑した。
私は初め、急に胸が大きくなったせいだと思った。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。勿論、彼女たちが笑う原因は、そこにあるのにちがいない。けれども同じ笑うにしても、胸がぺたんこだった昔とは、どことなく様子が異なる。見慣れた貧乳より、見慣れない巨乳が滑稽に見えると言えば、それまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。
(前はあんなずけずけ笑われなかったのに)
私はこう呟くことが増えた。そのように考え出すと、授業中でも遊んでいる時でも気が滅入ってしまうのだ。しかしその時の私に、その原因が分からなかったのも無理はない。
笑いというのはある意味残酷だ。TVに映る不細工なお笑い芸人を見て笑う。あんな顔で可哀そう、自分だったら絶対自殺するな、と多少同情しつつも面白いものは仕方がない。あるいはクイズで頓珍漢な回答をして、顔面粉まみれの罰ゲームを受ける芸人を笑う。可哀そうであるが自分は関係がない。ゆえに面白い。より不細工な方が、より酷い罰ゲームの方が興をそそられる。
これはいじめの傍観者の心理と非常に似ているのかもしれない。極端な話、お笑い芸人はクイズに正解することを求められていない。彼らがTVで恥をかかないと、視聴者は物足りないのだ。もっと失敗しろ。もっと恥をかけ。なぜなら、私たちには関係ないから。
第三者的立場のエゴイズムとは、かくも残酷なものである。私がなんとなく不快感を覚えたのも、このエゴイズムを多少なり感じ取ったからに他ならない。
キョウコと喧嘩した日から、私の機嫌はどんどん悪くなっていった。少しでも触れれば爆発しそうなほどにである。どうせ爆発するなら両の胸が木端微塵になって元の平地に戻ればいい、とさえ思っていた。喧嘩の原因はそれほどまでに最悪である。私が告白された男子生徒は、あろうことかキョウコの元カレだったのだ。彼は私の胸と比べて、元彼女であるキョウコの胸を散々馬鹿にしたらしい。私の胸が一か月前までどんな様だったかも知らず。
「あんたなんかドーピングしてるくせに!」とキョウコはわめき散らしたが、とんだ逆恨みである。
私の豊胸が薬によるもの、という噂を耳にしたのはその後である。例の錠剤を知っているのはリツ、キョウコ、ヒカリの三人しかいない。私は激怒し、三人を問い詰めようとしたものの、女子高の噂のスピードには勝てず、あっという間に私はゲートウェイ・ドラッグ常用者からヤク中、あげくにシャブ中までランクアップしてしまっていた。
私はいい加減、大きな胸が恨めしくなった。
ある夜の事である。その日は急に寒くなり、秋用の布団で私は丸くなり羽毛布団を出そうかどうか思案していた。すると、胸がいつになく熱い。なんだかむくんでいる気もする。
(やっぱりあの薬、危ない薬だったかな、飲まなきゃよかったかな……)
やっぱり止めときゃよかったかも、と思いつつ、腫れぼったい胸をさすりながら眠りについた。
翌朝、目をさますとやけに空がまぶしい。眠たい目をこすりながらカーテンを引くと、一面の銀世界が見えた。雪だ。そういえば室内の空気が澄みきっている。昨日は体がダルくてあんまり寝てないけど、少しテンションが上がってきた。きれいな空気を胸いっぱいに深呼吸。ほとんど、今まで体感したことのない感覚が私に訪れたのはこの時である。
私は慌てて胸に手をやった。手に触れたのは、昨日までのふくよかな胸ではない。いや、ふくよかどころではない、「ギネス・ワールドレコーズ」や、お正月のびっくり人間ショーで見るような巨乳、いや爆乳が胸にぶらさがっていた、というか、これが胸本体なのである。片方がゆうにメロン大である。
そうしてそれと同時に、初めて胸が大きくなった時と同じような、はればれした心もちが、どこからともなく帰って来るのを感じた。
(ここまでくれば、みんなどうやって笑えばいいかわらないよね)
私は心の中でこう自分に呟いた。Qカップの胸を冬の窓辺でたゆんたゆんとゆらしながら。